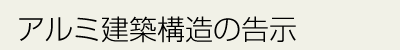これまでアルミニウムはサッシやカーテンウォール等、建築仕上げ材として使用されてきましたが、柱や梁など構造部材に用いる材料としては、建築基準法令上認められていませんでした。
そのためアルミニウムを構造部材に使用する場合は、従来から構造材料として認められていた鋼材や木材等とは違い、通常の建築確認申請による認可ではなく建設大臣(現国土交通大臣)の認定が必要とされていたため、時間と費用を伴う特別な手続きが必要でした。
今回の告示公布により、アルミニウムが鋼材等と同様、構造部材に使用できる材料として認められ、また構造計算に必要な各種許容応力度、及びアルミニウム建築物の構造方法に関する技術基準が定められたことによって、通常の確認申請で容易に建築が可能となりました。
告示の概要は以下の通りです。(ページ下部の資料欄に掲載している告示のタイトルをクリックすると、内容をPDFファイルにて御覧いただけます。)
<国土交通省告示第750号>
アルミニウム合金造の建築物は、延べ面積を従来は50㎡以下としなければならなかったが、200㎡以下に緩和された。
また、アルミニウム合金造の建築物の埋め込み形式柱脚に係る仕様規定は、構造計算により安全性が確かめられた場合は適用しないこととなった。
そして、アルミニウム合金造の建築物の仕様規定について建築士の設計に係る小規模建築物の場合、建築確認などにおける審査を省略できるようになった。
<国土交通省告示第607号>
アルミニウム合金造の建築物の構造部分の構造方法の技術的基準として、適用範囲、材料、圧縮材の細長比、柱の脚部、接合など10項目についての設計に必要な具体的な値が規定されている。
これら設計に必要な具体的規定は、アルミニウム合金の特性に即して基本的には鉄骨構造物の規定と同じ考え方で規定されている。カーポートなどの比較的軽微なアルミニウム構造に適用する上では、幾分の不都合もあるが、その点については現在国土交通省サイドと検討中である。いくつかの問題は内包しているが、これらの告示によってアルミニウム建築物が、通常の確認申請の枠組みの中で建築可能となった。
<国土交通省告示第410号>
アルミニウム構造の構造方法に関し構造計算では代替できない原則的な仕様規定が定められた。
即ち、(面積)規模に対する規定、接合部、圧縮材の細長比、柱の脚部形式、水平力対策その他細部の規定及び構造計算によって安全が確認できる部分に対し適用する構造計算の方法等、アルミニウム構造の構造方法に関し安全を確保するため、構造計算による確認と併せ適合要件とされる技術基準が定められた。
<国土交通省告示第409号>
建築物の構造計算において安全性を検討・確認する上で重要な指標として必要不可欠である使用構造材料に関する 「許容応力度」及び「材料強度」、 またそれらの算出に当たって基準となる「基準強度」が アルミニウム合金について規定された。
これにより、圧縮、引張り、曲げ、せん断の基本的な「許容応力度」、「材料強度」及び座屈等に関する「特殊な許容応力度」、「特殊な材料強度」が定められたため構造計算が可能となった。
<国土交通省告示第408号>
建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料、またその適合すべき品質に関する規格及び技術基準を定めた規定のなかに 「アルミニウム合金材」が加えられた。 また、その品質が適合すべき規格として JIS(H4000、4040、4100、4140、5202、Z3263)が規定された。
即ち、アルミニウム合金材が柱、梁、床版、屋根版等の 構造耐力上主要な部分に使用できる「指定建築材料」として認められた。 アルミニウム使用材料の品質規定とされるものである。