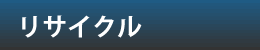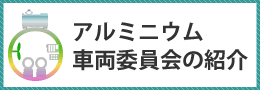1.はじめに
アルミニウムは、新地金を製造するために必要な電力量のわずか3%で再生地金を製造することが可能であり、リサイクルによって省資源、省エネルギー効果が得られます。日本において1962年にアルミ合金製車両が誕生して以来、その数は着実に増加し、2013年5月には2万両を達成致しました。
今後これらの車両の廃車が増加することとなり、リサイクル手法の確立は非常に重要な課題であると言えます。
2.アルミ合金の分別
アルミ合金の品質は成分組成で確保されていますが、再生地金を製造する際にアルミ以外の合金元素を抽出する技術が商業的に確立されていません。そのため再生用途に適した合金種毎に分別回収し、再生地金の成分を確認する必要があります。一方、分別しない場合は、手間もコストも抑制できますが、低品質地金として利用範囲が限定されるか、または純アルミニウムを大量に追加して全体を薄めて成分調整をしなければなりません。
次の項から、アルミニウム車両委員会にて東京メトロ有楽町線7000系初期型アルミ車両(1967年頃設計)および東京メトロ東西線05系車両(1988年頃設計)のリサイクル調査を行った結果を報告します。
また、リサイクル性の更なる向上を目的とし、使用合金を統一した有楽町・副都心線10000系車両についても紹介致します。3.東京メトロの有楽町線7000系車両のリサイクル性調査
東京メトロ有楽町線7000系車両のアルミ合金製車体(写真1、図1)は、1967年頃に設計された初期型の骨材と板材を溶接した構造であり、軽量化と高剛性を両立させるために強度の異なる数種類のアルミ合金を溶接したため、各部位のアルミ合金種別が統一されず分別がしにくい構造となっています。
このため、最近のモノアロイ化設計の車両に主に使用している6N01合金を製造するには、分別作業に手間がかかることと、かつアルミ新地金を大量に使用して大幅な成分調整が必要となります。よって、車体解体時には7000系アルミ合金を多く含む台枠部位と、5000系アルミ合金を多く含む側・妻・屋根構体を使用し2分割して別々に解体して再生合金化し、異種合金がなるべく混ざり合わないように工夫しました。
この解体から再生までの工程で、車体1両あたりのアルミ合金使用量のうち、80%程度を回収することが可能となりました。
アルミ再生合金は、ダイカスト材や高品質鋳物材にリサイクルしました。


写真1 有楽町線7000系 車体と類似の千代田線6000系量産車の車体
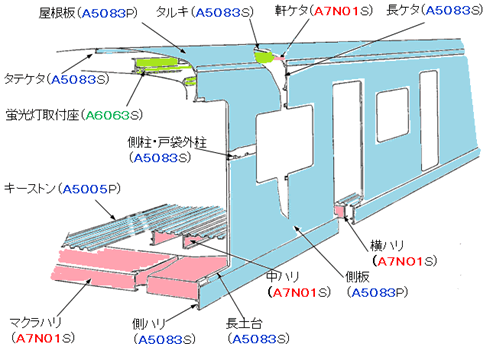
図1 有楽町線7000系車体構体部位と使用アルミ合金
4.東京メトロの東西線05系車両のリサイクル性調査
東西線05系(写真2、図2)は1988年頃に設計されており、6000系アルミ合金を主とした大型形材を使用しています。さらに部位別に使用合金がある程度分別されているため、合金毎の分別性も向上しています。リサイクル困難な7000系アルミ合金を多量に含む台枠両端部(端はり~中はり~枕はり)を除き、台枠中央部と側構体、および屋根構体は6000系アルミ合金が、妻鋼体は5000系アルミ合金の割合が高く他種合金の割合が少ないため、部位毎に分割してリサイクルすれば、新地金による成分調整が少ない展伸材や、多少の成分調整のみで再用可能な高品質鋳物材等に使用用途が拡大することが予測されます。
今回、この05系車両のリサイクル性について調査した結果、この解体から再生までの工程で90.7%の回収率を達成することができました。


写真2 東西線05系車体
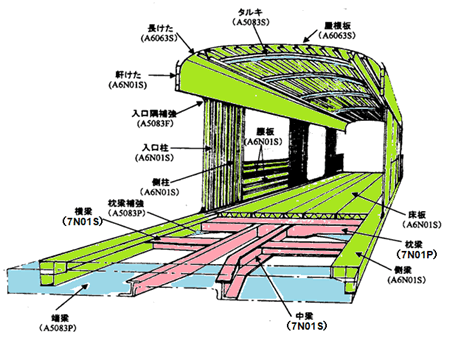
図2 東西線05系車体 構体部位と使用アルミ合金
5.これからのアルミ合金製車体の構造と使用アルミ合金
2006年度に設計された有楽町線・副都心線10000系車両のアルミ合金製車体(写真3、図3)は、リサイクル性の更なる向上を目的とし、使用合金を6N01材に統一したため、分別作業の手間が削減され容易に純度が高い合金を回収可能になると期待されます。
これ以降、基本的にアルミ合金製の通勤車両の車体はモノアロイ化(6N01材で製作)されているため、リサイクルが活発に実施されていくことが期待できます。

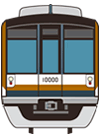
写真3 有楽町線・副都心線10000系車体
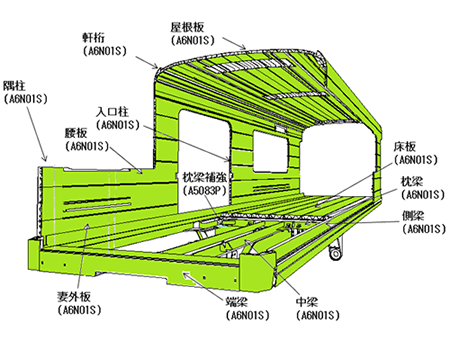
図3 有楽町線・副都心線10000系車体構体部位と使用アルミ合金
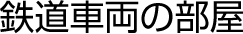
 リサイクル
リサイクル