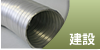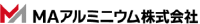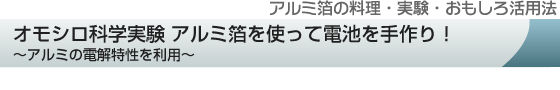アルミ箔の世界 HOME > アルミ箔の料理・実験・おもしろ活用法 >オモシロ科学実験:レモン電池
 |
|
||
| アルミホイルを10cm×15cm位の大きさに切り、テーブルに並べます。 |   |
|
| レモンを二つに切り、切り口を下にしてアルミホイルに乗せます。 | ||
| レモンにステンレス製のフォークを突きさします。 | ||
| アルミホイルの一端と、隣り合わせのレモンにさしたフォークとを、ワニ口付きのリード線でつないでいきます。 | ||
| 一番端のアルミホイルからのリード線と、反対側のレモンに刺したフォークからのリード線を、電子オルゴール(市販のバースデーカードなどに内蔵されています)の電池用-極と+極につなぐと、オルゴールが鳴ります。 |
|
||||
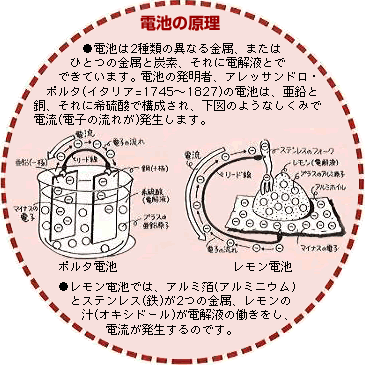 |
||||
|
備長炭2本、アルミホイル、ペーパータオル、食塩、水、リード線(ワニ口付き)3本、目玉クリップ2個、ボウル、模型用モーターとプロペラ
|
| ボウルに水と食塩を入れ、濃いめの食塩水を作ります。 |  |
|
| ペーパータオルを食塩水にひたし、よくしみ込ませます。 | ||
| 食塩水のしみ込んだペーパータオルを備長炭に巻きつけます(炭の一方の端4cm位は残しておく)。 | ||
| ペーパータオルの上から、備長炭に触れないようにアルミホイルを巻きつけ、一方の端を余らせて細くまとめます(-極)。 |  |
|
| 出ている方の備長炭を目玉クリップではさみ、リード線につなぎます(+極)。 これで、炭素とアルミニウムを電極とした電池の完成です。 |
  |
|
| 模型用のモーターをつなぐと、勢いよく回ります。アルミホイルを巻いた備長炭を強く握ると、接触がよくなりさらにパワーアップします。 | ||
|
アルミ箔皿、粒状活性炭(冷蔵庫用脱臭剤の容器から取り出す)、食塩、水、コップ、ペーパータオル、はさみ、リード線(ワニ口付き)2本、豆電球
または点滅球(1.5V)
|
| アルミ箔製の皿の上に、皿のサイズより一回り大きめに丸く切り抜いたペーパータオルを2枚重ねて敷きます。 |  |
|
| (1)のペーパータオルに濃いめの食塩水(コップのぬるま湯に大さじ2杯の食塩を混ぜて溶かす)をかけ、よくしみ込ませます。 |  |
|
| (2)の上に、粒状活性炭を平らに敷きつめます。 |  |
|
| (3)の上に次のアルミ箔皿をのせ、これで1個の電池が完成です(アルミ箔の皿同士が接触しないようにします)。 この上に(1)から(4)の順でどんどん重ねていけば、よりパワフルな電池になっていきます。 |
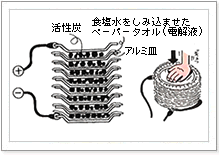 |
|
| 一番上のアルミ箔皿(+極)と一番下のアルミ箔皿(-極)から、リード線で豆電球につなぐと点灯します。 | ||
| このときも、接触をよくするため、上から手のひらで強く押しつけると、明るさが一層増します。 |   |
|
| 材料の備長炭、アルミ箔皿、実験用モーター、リード線、豆電球などは、ホームセンター、模型店などで購入するか、理科の先生に相談してみて下さい。 参考資料として、(財)科学技術広報財団制作"おもしろ理科実験ビデオ"シリーズの「教えて!ボルタ先生」があります(ダビングサービス+送料で1600円)。 お問い合わせは同財団(TEL:03-5501-2351)まで。 |