| ■アルツハイマー病とは |
それではアルツハイマー病とはどういうものか,というお話をいたします。
今,申しましたようにアルツハイマー病は脳が全体的に障害される,全体的な病気である。下は正常の74才で亡くなられた方の脳で,脳の病気は一切なかった方です。それに対して上はアルツハイマー病でなくなられた方で80才弱の方です。このように,脳が萎縮して,萎縮したために脳のしわが深くなり,溝が深くなって,しわがたくさんある,という状況です(図1)。今いいましたように認識の中枢は頭頂葉にある,視覚の中枢は後頭葉にあります,それから側頭葉は記憶を,それから判断するというのが前頭葉,というふうに大体大きく役割分担というのがあります。
今,これを縦に切って前の方から見てみると(図2),コントロールは下です。この外側のちょっと色の濃いところが灰白質と言って,神経細胞がいっぱいつまっています。脳で一番大事な神経細胞体が存在しているわけです。これが側頭葉でその内側に,巻き込むようにしてあるのが海馬といって記憶の最も大事なところです。それからこういうところは基底核といって運動の調節を司るところです。パーキンソン病というのはこういうところの症状を云います。
アルツハイマー病というのは海馬から大脳の灰白質にある神経細胞が障害されて死んでいくものですから脳が萎縮していくというわけです。ここに脳室という部屋がありまして,脳室には水がたまっています。この脳が萎縮する結果,脳室はこのように拡大していく。特に大事なのはここの部分でして,海馬がもうここはほとんど見られない,これだけ本来あるべきものがペらんペらんになっているのです。そこにある,本来脳室というのは見えないぐらい小さいものなんですが,こんなに開いている。
|
|
 |
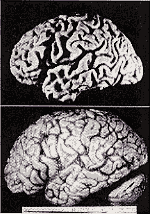
|
| 図1 |
アルツハイマー病の脳(上)と
正常コントロールの脳(下)
(国療犀潟病院巻淵隆夫先生提供)
|
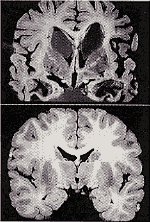
|
| 図2 |
アルツハイマー病(上)の脳の断面に海馬の萎縮が見られ,脳室が拡大している。下は正常対象
(国療犀潟病院巻淵隆夫先生提供)
|
|