
|

|

|
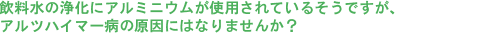


|

|

|

|



|

|

|

|



|

|

|

|



|

|

|

|
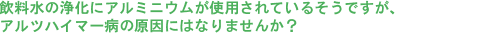


|


|

|

飲料水は河川や地下水を採取して各家庭等へ供給されますが、この原水の濁りを取り除くため硫酸アルミニウムや、ポリ塩化アルミニウムを凝集剤として使用します。
凝集剤の大部分は濁りとともに沈降、ろ過により除かれ、浄化後の水にわずかのアルミニウムがのこりますが、アルミニウムがアルツハイマー病の原因や、アルツハイマー病に近似の脳の変化を起こすという科学的根拠はなく、WHO(世界保健機構)でも「アルツハイマー病にアルミニウムが主たる役割を果たしている証拠はない。アルミニウムはヒトを含むいかなる種においてもアルツハイマー病の病変を示すことはない。」としています。
|

|

|

|



|


|

|

愛知県衛生課が平成2年までに行った調査では、浄水中のアルミニウム量は0.02〜0.18mg/Lの範囲にあります。Q5でみた通り、食品などから摂取しているアルミニウムの量と比べると非常に少ない量であるといえます。
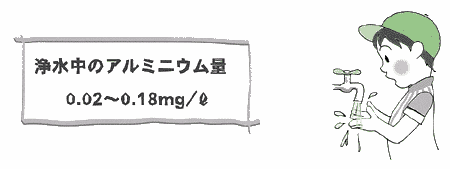
|

|

|

|



|


|

|

飲料水中のアルミニウム濃度とアルツハイマー病との関係についての研究は数ヵ国で行われ、「水道水中のアルミニウム濃度が高い地域でアルツハイマー病患者の発症率が高い」とした報告もありますが、その知見の妥当性について方法論的に弱点があり、疑問が持たれています。英国ではマーチン等の学者により、1989年に「飲料水中のアルミニウム濃度が0.11mg/Lを超える地域では、0.01mg/Lより低い地域に較べて 1.5倍の疾病リスクがある」として、飲料水中のアルミニウムとアルツハイマー病の相関についての研究レポートが出されました。
 1997年に同氏等により、そのデータ収集に用いられた方法論の批判に対して、より正確な技術による再調査がなされました。この第2の科学的に妥当な調査で、マーチン等は1989年の結果を再現することができませんでした。 1997年に同氏等により、そのデータ収集に用いられた方法論の批判に対して、より正確な技術による再調査がなされました。この第2の科学的に妥当な調査で、マーチン等は1989年の結果を再現することができませんでした。
|

|

|

|



|


|

|

飲料水の基準についてWHO(世界保健機構)はガイドラインを1993年に改正し、加盟各国に勧告しています。128項目のガイドライン値の中でアルミニウムは「飲料水としての性状目標値」として美的及び感覚的観点から 0.2mg/L以下としています。これは水中のアルミニウム濃度が高くなると白濁を生じるためです。日本でもWHOの動きに合せ水道水の水質基準を1992年に見直し改正しました。アルミニウムはこの中でおいしい水の供給を目指して決められた快適水質項目として0.2mg/L以下としています。飲料水中のアルミニウム濃度についてはこのように決められていますが、いずれも水道水の味と外観に関する値であり、健康に関するリスク基準として定められたものではありません。

|

|

|